top of page
笑下村塾新聞
NewsPaper
社会問題や政治をもっと身近に。
インタビューやレポートを通じて、課題解決のヒントを発信します。
検索


【前編】高校生をエンパワーメント!特別ゲストを招いたオンラインワークショップを開催しました。
こんにちは、スタッフのとがです。群馬県高校生リバースメンターオンラインプログラムにて、高校生が自ら社会を変える力を身につけるため、特別ゲストを招いてエンパワーメントをテーマにしたワークショップが開催されました。一人目のゲスト、遠藤まめたさんは「Change.org」のキャンペーンサポーターとして、オンライン署名の力を使って社会を変える方法を紹介。続いて、二人目の石原花梨さんが「中高生食堂」を通じて、孤食問題に取り組んできた経験を共有しました。最後に、金澤伶さんが学費値上げ反対緊急アクションについて語り、それぞれの視点から高校生たちをエンパワーしました。 ~一人目のゲスト:遠藤まめたさん~ 一人目のゲストは遠藤まめたさん。オンライン署名サイト「Change.org」のキャンペーンサポーターして署名での社会の変え方をお話して頂きました。 ■小学生も使う「オンライン署名」とは? 「最近は、ネット署名を使って発信する高校生や小学生なども増えてきています。ネット署名は、誰でも気軽に使えるツールななってきています」と、遠藤さんは冒頭で語り、現在の若い世代が

笑下村塾
2024年9月16日読了時間: 9分


リバースメンターの高校生が8bitNewsに出演しました!
こんにちはスタッフのとがです。たかまつななが元NHKキャスターでジャーナリストの堀潤さんに、8bitNewsにお招き頂きました! 実際に参加した高校生3人をゲストにお招きし、今何を思うのか?インタビューして頂きました。 リバースメンターとは? 高校生が首長の相談役となって、政策に若者の声を反映させるために行う取組です。リバースメンターとなった高校生は自身のテーマを現役官僚やコンサルタントからアドバイスをもらい、国内・海外の事例を調べ問題意識を深堀りして、アイディアを磨き、首長に直接プレゼンで熱い思いを伝えます。ワークショップではテーマの構造化や海外国内の事例の調査などで新たな視点でテーマを掘り下げる力を養います。その他、知事からの相談に直接乗って意見交換をする場にも参加をして、思いや声を県に届けます。 群馬県リバースメンターの様子 古賀リバースメンターの様子 「eスポーツで世代を超えたコミュニティ作りをしたい」倉林虎輝さん 「eスポーツで世代を超えたコミュニティ作りをしたい」というテーマで2023年度の「群馬県高校生リバースメンター」として参加し

笑下村塾
2024年9月12日読了時間: 6分


「すぐに解散総選挙」「18歳から被選挙権を」自民党総裁選、野田聖子が見据える日本の未来とは?
自民党総裁選挙への立候補の意向を表明している衆議院議員、野田聖子さん。総理大臣になったら?解散総選挙は?政治とカネの問題への対応は?YouTube「たかまつななのSocial Action!」で 話を聞きました。 (取材:たかまつなな/笑下村塾) ※取材は2024年9月6日に実施しました。 「人口急減」を直視する総理大臣に ーー総裁選への立候補の意向を表明されました。まずはその理由についてお聞かせください。 野田:私、(立候補が)4回目なんですね。政策を訴えていくことの一つの大きな道が総裁選への取り組みかなと思っているので、自分たち、仲間たちが伝えたいことを伝える役割を果たしていこうと思って頑張ってます。今回はたくさん手を挙げているので、推薦人の分配が大変そうですね。 ーー20人の推薦人の確保まであと少しという感じでしょうか? 野田:いつもあと少しなんですよ。20の壁は何回か経験したんですけど、そのときの風の流れみたいなのもあって、みんなが苦労してたどり着く絶妙な数字だなと思っています。 ーー野田さんが総理大臣になったら何を実現したいですか。..

笑下村塾
2024年9月11日読了時間: 12分


たかまつなながIBM Future Design Lab.の勉強会でお話させて頂きました!
こんにちは、スタッフのとがです。 IBM Future Design Lab. 藤森 慶太さんにお招き頂き、社内勉強会FDL学にてお話させていただきました。いくつかたかま つが頂いた質問やお話したことををこちらにまとめました。 内発的モチベーションをどう保つか? 内発的モチベーションとは、自分自身から生まれる動機であり、人に言われてやる外発的モチベーションとは対照的です。内発的モチベーションをどうやって維持しているかという質問に対し、たかまつは「誰もやらないからこそ自分がやる」という使命感を抱いて取り組んでいると答えました。 さらに、たかまつは勇気を持って声を上げた人々と連帯し、社会の不正や問題に対して積極的に声を上げることを重要視しています。たかまつの一つの活動例が、「 繰り返される性被害と人権侵害 #芸能人を守る法律を作ろう」というキャンペーンです。自身も芸能界でのセクハラやパワハラの経験があり、そうした問題に対して「おかしいことには立ち向かう」という強い信念を持っています。こうした活動を通じて、たかまつは内発的モチベーションを保つよう頑

笑下村塾
2024年9月9日読了時間: 5分


笑下村塾の仲間を募集~社員、インターン、副業人材募集中!~
こんにちは、スタッフとがです。私たち笑下村塾では、若者の政治参加を促進するために一緒に働いてくれる仲間を募集しています。私たちの活動に興味があり、社会に良い影響を与えたいと思っている方々のご応募をお待ちしています。 詳しい募集要項:...

笑下村塾
2024年9月9日読了時間: 4分


「先生の過労」をテーマにたかまつななが取材を受けました! AERA 9月24日発売号に掲載予定です
こんにちはスタッフのとがです。「先生の過労」をテーマにたかまつななが取材を受けました。その模様はAERA 9月24日発売号紙面とWEBでも発売予定です。非常に重要なテーマについてお話させて頂きました。ぜひご覧ください。 恩師の「死にたい」という言葉 たかまつが先生の過剰労働に意識を持つようになったのは、大学院生の時に昔の担任の先生から深夜に「死にたい」という電話を受けたことがきっかけです。その時、なぜこんなことになったのかと驚いて母校を調べてみると、過労で辞めていった先生が他にもいることがわかったそうです。このことが、全国的に起きている深刻な問題だと知り、強く関心を持ってそれ以来取材や発信を続けています。 なぜ笑下村塾「先生の過労」に取り組むのか? 私たち笑下村塾のメインの活動は「主権者教育」です。主権者教育を推進しても、先生たちがすでに過労状態であり、その中で新しい取り組みを導入するのは現実的に無理だと痛感しています。学校の先生への取材もしながら、現場の過酷さを実感し、この問題にも深く関わるようになるようになりました。 過労死ラインを超える

笑下村塾
2024年9月7日読了時間: 3分


「閣僚の半分を女性にする」自民党総裁選に意欲を示されている野田聖子さんを取材しました
こんにちはスタッフのとがです。2024年9月6日、自民党総裁選の意欲を示されている野田聖子さん。総裁選について、人口減少への対策、女性の社会進出と働き方改革、岸田政権の評価、自民党の抱える課題、選挙制度と女性の役割、若者の政治参加などなど日本の未来についてYouTube たかまつななのSocial Action! で伺いました。 総裁選への意欲は? もし挑戦されるとしたら、今回で4回目の自民党総裁選。総裁選に出ることは、自分たちの政策を訴えるための大きな道とおっしゃっており、推薦人集めは「あと少し」と苦労もある様子でした。それでも、政策を伝える役割を果たすため、仲間と頑張り続けるとのことです。 総理大臣になったら何をやりたいか? もし総理大臣になったら、野田さんはまず「人口急減」という問題に取り組みたいと考えていました。これまでの政治は人口減少の現実に向き合ってこなかったため、今こそ直視すべきだと強調されていました。さらに、総理になったらまず「閣僚の半分を女性にする」「立候補年齢を18歳に引き下げるべき」など政策案も伺っていきました。 取材

笑下村塾
2024年9月6日読了時間: 1分


高校生が社会を変える!?ワークショップの様子をレポートします!〜古賀市リバースメンター〜
こんにちは!笑下村塾スタッフのとどころです。 8月25日に福岡県古賀市で行われたリバースメンタープロジェクトオフラインワークショップの様子をご紹介します! 今回は第3回のワークショップです! 市長との提言会で意識してほしいことについて 2023年度に群馬県で行われたリバースメンターの事例を見ながら高校生たちがワークショップへ取り組む様子が...! 提言会までに必要な提言シート・提言会の時に使用するスライドの作成・提言する時のポイントなど... 提言会のイメージを掴めているような印象を見ることができました。 また、今回のワークショップの中では、ツールに関する基礎知識などについての説明も... 提言シートやプレゼン用資料の作成ツールについての説明中にも 高校生たちが熱心にワークショップに取り組む姿を見ることができました...!! 「LGBTの人も暮らしやすい社会にしたい」「英語試験の受験料を補助したい」「交通安全の課題を解決したい」「ヤングケアラーに寄り添う社会にしたい」などそれぞれの提言に向けて少しずつ進んでいるような印象を持ちました!...

笑下村塾
2024年8月30日読了時間: 2分


高校生たちが知事に未来への提言を直接発信!〜群馬県リバースメンター〜
こんにちは!笑下村塾ボランティアスタッフのスギヤマです。 8月9日に群馬県庁にて、高校生リバースメンターによる山本知事への提言会が行われました。山本知事に直接考えをプレゼンすることができる機会です。6月にリバースメンターとしての活動がスタートしてから約3ヶ月。この間、高校生たち一人一人が自分たちの提言について真剣に向き合い、考えを深めてきました。 自身の提言をつくる中で、高校生たちは試行錯誤を繰り返していました。自分の提言が独りよがりな考えになっていないか、身の回りの友達から専門家まで、様々な立場の人たちにアンケートを取ったり話を聞いたりすることも大切にしました。その姿からは、「みんなにとって、よりよい社会を作っていきたい!」という想いが伝わってきました。 初めての経験もたくさんあり、なかなかうまくいかずに壁にぶつかったこともありましたが、その度に自分が大切にしたいことは何か、初心を思い出しながらここまで進むことができました。 提言会当日は、今まで切磋琢磨してきた仲間たちと「頑張ろう!」とお互いに声を掛け合う姿から、高校生たちの並々ならぬ意欲が伝

笑下村塾
2024年8月25日読了時間: 2分


高校生が市長にアドバイス?!古賀市リバースメンタープロジェクト始動!!
こんにちは!笑下村塾の麻生です。 今日は7月25日にリーパスプラザ古賀で行われた古賀市リバースメンタープロジェクト委嘱式の様子をレポートします! この日は古賀市リバースメンターの高校生たちが初めて市長に会う日でした。 田辺市長から委嘱状を手渡される高校生たち...中々緊張した面持ちです。 それも、そのはず。彼女らは未来の古賀市を託されたリバースメンターなのです! 彼女らはこれから3か月間、市長の相談役(メンター)となって古賀市の問題を解決する政策を考え、11月の政策提言会で市長に提案する予定です。 高校生にとっては初めて会う政治家... みんながそれぞれ感じている問題意識をきちんと受け止め、その問題にはどういう背景があるのか、古賀市はどんな政策をしているのか、分かりやすく伝えてくれる田辺市長。 「お金をいっぱいもらってるイメージ...」 「政治家ってもっと悪い人だと思ってた」 など政治家にはネガティブなイメージを持っていた高校生たち。 人のせいだと決めつけるのではなく、その根元にある構造やしくみの問題に気づくことから政策立案は始まっていきます。.

笑下村塾
2024年8月4日読了時間: 2分


【2024年都知事選】候補者たちの姿から見えた希望と課題。民主主義の危機に私たちができること。
2024年7月7日、東京都知事選挙の投開票が行われました。 結果は、現職の小池百合子氏の3選という、ある程度予想されたものではありましたが、今回の選挙戦は、これまでの都知事選とは異なる様相を呈しており、多くの課題や希望が浮かび上がるものとなりました。 私自身、投開票日の前日、7月6日に、小池氏、蓮舫氏、石丸氏、安野氏、田母神氏の5人の演説に実際に足を運び、それぞれの陣営の熱気や有権者の反応を肌で感じてきました。そして、その経験を通して、日本の政治、そして民主主義の未来について、深く考えさせられることとなりました。 今回は、都知事選を通して見えてきたものを、それぞれの候補者の姿と共に振り返りながら、これからの政治に求められる役割について、より深く掘り下げて考えていきたいと思います。 私が一番伝えたいのは、選挙戦自体の振り返りよりも、これからの政治や主権者教育なので(都知事選を振り返りたい方は1から6までも読んでいただきたいですが)、7から読んでいただいても分かるようにしました。 1:小池百合子氏:揺るぎない支持基盤と、見え隠れする「権力の疲労」..

笑下村塾
2024年7月16日読了時間: 9分


より多くの人に知ってほしい 初めて記者会見を開いた理由
※共同通信配信の有料メディア向けコラムから転載( 2024年02月19日配信) 「社会は変えられる」。そう思う子どもたちを増やすのが、私たち笑下村塾の夢だ。若い人の政治参加を促す活動に取り組む中で、海外の子どもに比べ日本には「変えられる」と思う若者が少なく、行動にもつながっていないと考えるようになった。 ひるがえって自分はどうか。子どもの頃に「変えられる」と思っていたのか。どこかに無力感を抱いていなかったか。今も本当に「変えられる」と信じ、日々活動できているのだろうか。 この連載でも何度か書いた「高校生リバースメンター」プロジェクト。10代の少年・少女が、知事のメンター(相談役)として政策提言をする活動で重視したのは、社会を変える経験をすることだ。「社会を変える方法はたくさんある。変えてきた若者がこんなにいる。みんなも社会を変えている」。これまで彼らにそう伝えてきた。 もっともっと自分にできることはないか。そう考えた私は先日、人生で初めての記者会見を開いた。その思いを最後につづりたい。 私は社会問題解決型の番組を作りたいと思い、新卒で入っ

笑下村塾
2024年7月16日読了時間: 4分

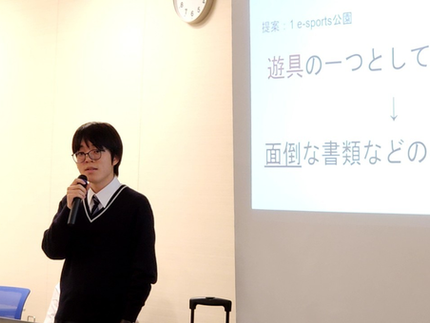
eスポーツでシニア世代と交流?! 地域活性化へ高校生が提言
※共同通信配信の有料メディア向けコラムから転載( 2024年02月05日配信) 地域で世代間交流の場がない。その解決策の一つとして、シニアと若者が一緒にゲームを楽しもうと提言した人がいた。なんと、それは高校生だ。 「eスポーツ(esports)」とは、「エレクトロニック・スポーツ」の略でコンピューターゲームやビデオゲームを使った対戦を指す。地域の活性化に寄与するとして、eスポーツを事業化する地方自治体も出てきている。群馬県もその一つで「eスポーツ・クリエイティブ推進課」を設置し、群馬のブランド力向上に取り組んでいる。 群馬在住の高1男子、倉林さんは「グンマeスポーツアワード(GeA)」への参加をきっかけに、eスポーツで地元を活性化させたいと考えるようになった。GeAでは、シニアも若者と同じようにeスポーツを楽しんでいた。だが、世代別で部門が分けられてシニアと若者が直接競う機会はなく、年齢を超えた関わりが持てるeスポーツの良さを生かしきれていないのでは、と疑問を感じた。 群馬県もeスポーツの魅力に「年齢、性別、身体能力等の差が少ない」点を挙げ

笑下村塾
2024年7月15日読了時間: 4分


野外フェスのような台湾総統選!
※共同通信配信の有料メディア向けコラムから転載 (2024年01月22日配信) 1月13日に台湾で総統選および、日本の国会議員に当たる立法委員選の投開票が実施された。4年に1度の選挙だが、台湾には期日前投票や不在者投票・在外投票の制度がない。にもかかわらず、投票率は7割を超えた。中には「留学先から選挙のために帰国した」という有権者も。アジアの民主主義の教科書とも呼ばれるその実態に迫った。 まるで野外フェス。現地を取材してそう思った。最大野党、国民党の演説集会は、横浜アリーナのような会場で開かれた。 与党の民主進歩党(民進党)の街頭演説会は、主催者発表で10万人を超える支持者らが詰めかけた。 「近所だから来た」「民進党を応援しているから」。政党のグッズが販売されるなど、家族や友人、恋人同士で気軽に訪れやすい雰囲気だ。「昨日の民衆党(野党第2党の台湾民衆党)の集会では、35万人が集まりました」というニュースを見て驚いた。投開票日の前日、若い世代に人気の民衆党の演説会は、大勢の若者であふれかえった。 投開票日、民進党の党本部前には大型のスクリーン

笑下村塾
2024年7月14日読了時間: 5分


「リバースメンター」が知事に提言! 子宮頸がんワクチンを広めたい高校生の思い
※共同通信配信の有料メディア向けコラムから転載( 2024年01月08日配信) 「HPV! HPV! ワクチン ワクチン 検診へGO!」 2023年11月23日、群馬県庁。多くのカメラの前で、山本一太知事は2人の女子高校生とTikTokを踊っていた。いずれも知事から任命された「高校生リバースメンター」。大人では到底思い付かないアイデアを提案するため日々活動している。 高校生リバースメンター制度は、23年7月に全国初の取り組みとして始まった群馬県と笑下村塾の共同プロジェクトである。本連載でも同年9月に一度取り上げている。 「リバースメンター」とは文字通り、高校生が立場を逆転させ、知事のメンターに就任するというものだ。スタートから半年近くがたち、23年11月には知事への提言会も行われた。この間のメンバー10人の活動を整理しながら、改めてこの事業の効果と意義について考察する。 (注)リバースメンター 1990年代後半に米国のゼネラル・エレクトリック(GE)社が始めた人事研修制度。若手社員が先輩社員に対し、逆(リバース)に相談役(メンター)として

笑下村塾
2024年7月13日読了時間: 6分


行政とタッグを組む?! ドイツの生徒会とは
※共同通信配信の有料メディア向けコラムから転載( 2023年12月25日配信) ドイツでは、州ごとの生徒会連合が存在する。一つの学校だけで生徒会活動を完結させず、地域の学校が連携し合い、政治家や自治体に生徒の声を届けることを可能にしている。自分たちの生活空間である学校を自らの手で変える仕組みは、主権者としての意識を育む場として、とても有効に機能していると言えるのではないだろうか。今回は、ドイツの生徒会について紹介したい(取材は2022年9月)。 市役所で生徒会代表選挙 北部ニーダーザクセン州のガルブセン市にある中高一貫校「ヨハネス・ケプラー・ギムナジウム」。21年から生徒会長を務め、同市の生徒会長代表でもある18歳のヤン・レーマンさんに話を聞いた。生徒の日々の問題を解決するために、学校や自治体と連携しながら活動しているという。 「私は生徒会長として常に生徒のために何かを変えようと頑張っています。うまくいくときや、そうはいかないときもあります。いつもガルブセン市と相談しなければいけませんし、それが私の仕事でもあります」 この学校では、生徒会長

笑下村塾
2024年7月12日読了時間: 4分


「ランチトーク」で子どもの声を市長に
※共同通信配信の有料メディア向けコラムから転載( 2023年12月11日配信) 4月に施行された「こども基本法」で、国や自治体は子どもの声を政策に反映する仕組みを作るよう義務付けられた。子どもの意見表明権をどう担保するかという議論は、今や世界で重要なトピックの一つになっている。日本でもこのような動きが出てきたことに感動すると同時に、実際に声を聞く難しさも痛感している。 そうした中、茨城県行方(なめがた)市では市長と小学生が一緒に給食を食べる「ランチトーク」が早くから行われてきた。今回は、若者の声を聞く同市のユニークな取り組みを紹介したい(取材は今年2月13日)。 素直な気持ちを聞く場 「同じものを食べることが大事ですよ」。子どもたちと同じ学校給食を市長室で口に運びながら教えてくれたのは、行方市長の鈴木周也さんだ。この日のメニューは、ご飯、牛乳、鳥の照り焼き、切干大根の中華炒め、イワシのつみれ汁、いよかんゼリー。2016年度にランチトークを始めた理由をこう話した。 「教室に行って授業のような雰囲気だと、どうしても子どもたちが緊張してしまう。そ

笑下村塾
2024年7月11日読了時間: 5分


ドイツで行われている平和教育って?
※共同通信配信の有料メディア向けコラムから転載( 2023年11月27日配信) ロシアのウクライナ侵攻が始まってから1年8カ月が過ぎた。イスラエルでは「戦争」が始まり、第三次世界大戦の引き金になるのではないかと緊張感が走っている。しかし日本では、戦争は二度と起こしてはならないと誰もが知りつつ、具体的にどのようにすれば良いのか分からない人が多い。これまでは戦争の悲惨な体験を聞き、平和を祈る教育が主流だった。だが戦後80年近くがたって直接的な記憶の伝承が困難となり、それだけで十分とは言えなくなった。昨年のウクライナ取材で聞いた人々の生の声をヒントに、私が提唱してきた「平和をつくる教育へのアップデート」が必要ではないだろうか。昨年秋、平和教育が進んでいる国の一つであるドイツの歴史の授業について取材した。この国でどのような平和教育が行われているのかを紹介したい。 歴史は現在の価値観の「ものさし」 北部ニーダーザクセン州の中高一貫校で、高校の歴史と経済の授業を(取材当時の)4年前から担当している教師ミヒャエル・ブッシュ氏にお話を伺った。ブッシュ氏は、歴史

笑下村塾
2024年7月10日読了時間: 5分


生徒も参加して何でも決めるドイツの「学校会議」とは?
※共同通信配信の有料メディア向けコラムから転載( 2023年11月13日配信) ドイツでは多くの学校が、学校会議という制度を設けている。州によって違いはあるが、学校運営全般、授業、校内外行事、あるいは登下校、就学援助、トラブル防止に至るまで幅広いテーマが議題となる。最も目を引くのは大人だけではなく、生徒も対等な立場で参加するというところだ。私が取材したベルリン州では、最高意思決定機関という位置付けで、校長の選任まで担っているというから驚きだ。子どもたちも自分たちの学校のトップを選ぶ決定権を委ねられているのだ。ベルリン州当局の学校会議担当者で、自身も親代表として参加した経験があるマティッヒ・クローネ氏に話を聞いた。 校長も自分たちで選ぶ 学校会議は、ベルリン州法の「学校法」によって設置が義務付けられている。メンバーは校長1人、教職員4人、親4人、生徒4人に外部講師1人で、計14人の構成だ。生徒代表は生徒が、親代表は親がそれぞれ選ぶ仕組みになっている。そして外部講師は誰でも推薦でき、多数決によって決める。生徒代表は、各クラス代表が2人選ばれ、その中

笑下村塾
2024年7月9日読了時間: 5分


政治家の発言を疑う高校生たち スウェーデンの批判的授業とは?
※共同通信配信の有料メディア向けコラムから転載( 2023年10月30日配信) スウェーデンが日本と比較して「若者の政治参加先進国」であることは、これまで実例を挙げつつ何度も指摘してきた。子どもたちが、大人たちからの信頼を基に、自分たちのことを自分たちで決める学校運営をしていること、すなわち「学校内民主主義の浸透」も優れた主権者教育になっている。 生徒代表者に自分たちの思いを託す。信じているからこそ学校内民主主義が成り立っている。身近な実感があるから、現実社会の行政や政治家に対する信頼も高い。 一方で、高校生たちと話して気付いたのは、バランス感覚も兼ね備えていることだ。自分たちの代表者である政治家も、同じ人であるからこそ「信頼しながらも疑う」というリアリズム。 「政治家はうそをつくし、情報を自分が伝えたいようにねじ曲げる。情報は、誰がどんな目的で言ってるのかを見極め、1次情報を探せばいい」と厳しい言葉を耳にした。彼、彼女らは授業で、批判的に資料を読み解く方法を学習していた。民主主義は、批判的思考により支えられる。スウェーデンで実践されてい

笑下村塾
2024年7月8日読了時間: 6分
bottom of page